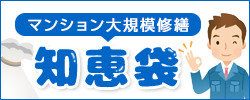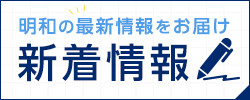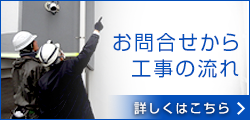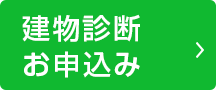マンション大規模修繕 知恵袋
2025.06.26
マンション大規模修繕工事18年サイクルのご提案 2025.06.26
仙台市内では分譲マンションが1577物件(2024年現在)と言われていますが、築年数の長期化に伴い第2回目の大規模修繕工事を迎える建物が増加しており、全体の施工物件毎年増加の傾向に有ります。第1回目の大規模修繕工事は管理会社主導で行われるケースも多く、資金計画的には予算通りに完了する事が多いと思いますが、第2回目以降の大規模修繕工事の場合は当初の予算を上回るケースも多く、特に管理会社やコンサルタント作成の修繕設計を修正せざるを得ないケースが散見されます。
計画を修正又は変更する場合には工事範囲の変更や分散化が検討課題となりますが、最も問題なのが資金計画に狂いが生じてしまう事に有ります。最近の資材や職人不足による人件費の高騰により、予想外の工事費の高騰が現実の問題となっています。その為、既存の長期修繕計画の修繕工事サイクルの見直しを図り、より無駄のないコストパフォーマンスに優れたマンションの大規模修繕工事を目指す動きとなり、修繕サイクルを長期化により合理化と経費の縮減を図る方向が注目を浴びています。
最近の国土交通省の推奨するガイドラインも12年から12~15年へと修正されていますが、大規模修繕工事のサイクルを12年から18年に変更するということは、長期的な視点での綿密な計画と、居住者様への丁寧な説明が不可欠となります。修繕積立金の値上げも伴う可能性が高いため、以下の対応策を総合的に検討することをお勧めします。
1.現状の把握と詳細な分析
 まず、現在のマンションの状態を徹底的に把握し、12年サイクルから18年サイクルへの変更が、建物にどのような影響を与えるかを詳細に分析する必要があります。
まず、現在のマンションの状態を徹底的に把握し、12年サイクルから18年サイクルへの変更が、建物にどのような影響を与えるかを詳細に分析する必要があります。建物診断の実施
専門の業者による詳細な建物診断(外壁、屋上、設備など)を実施し、劣化状況を正確に把握します。特に、現状のまま18年サイクルに延長した場合に、劣化が進行しやすい箇所や緊急性の高い補修が必要となる可能性のある箇所を特定します。
長期修繕計画の見直し
現行の長期修繕計画をベースに、18年サイクルに変更した場合の劣化予測、修繕項目、概算費用を詳細に盛り込んだ新たな長期修繕計画を作成します。
修繕積立金の分析
現行の修繕積立金の積立状況、将来の不足見込み額を詳細に分析します。18年サイクルに変更することで、単年度あたりの修繕費用は減るように見えても、次回の修繕までの期間が延びるため、その間に必要な補修費用や、最終的な修繕費用総額がどうなるかを試算します。
2.長期修繕計画の策定と費用シミュレーション
 18年サイクルへの変更を前提とした、具体的で実現可能な長期修繕計画を策定し、費用シミュレーションを行います。
18年サイクルへの変更を前提とした、具体的で実現可能な長期修繕計画を策定し、費用シミュレーションを行います。修繕項目の優先順位付けと分散化
18年サイクルに延長するにあたり、劣化が懸念される部位や緊急性の高い箇所については、18年を待たずに計画的な部分修繕や予防保全を行うことを検討します。例えば、シーリング材や防水層の一部補修など、比較的軽微な修繕を中間期に行うことで、大規模修繕時の負担を軽減できる可能性があります。
部位ごとの耐用年数の把握
建物の劣化の進行は部位ことにそれぞれ異なり、一律な耐用年数ではありません。特に外壁改修・塗装・防水・シーリング・等のケミカル製品を使用した材料又は資材は特に紫外線や風雨に影響を受けやすく、また、環境や過去の修繕・管理の状況により耐用年数は建物により異なります。その為、屋上防水・外壁改修・鉄部塗装・シーリングなどは継続的な調査や判断が必要です。
大規模修繕工事と小・中修繕工事の分類
大規模修繕工事では足場を必要とする工事と必要としない工事が有ります。足場を必要とする工事は緊急又は優先されるべき工事とされ、外壁・外部階段・バルコニー内床・壁など、主に雨掛り箇所又は各戸別対応が困難な箇所が該当します。半面、屋上・ルーフバルコニー・共用廊下などは足場を必要としないケースも多く、工事の優先度としては低くなります。
その為、足場を必要とする工事を18年サイクルの大規模修繕工事とし、足場を必要としない小・中修繕工事は切り離して修繕時期を設定します。このように工事を細分化する事により、劣化の状況に応じた無駄のないコストパフォーマンスに優れた工事が可能となります。
結果的には、30年の長期修繕計画に沿った運用により、ロングコストを大幅に削減した計画を実行する事が出来ます。
新技術・新工法の導入検討
耐久性の高い建材や長寿命化に貢献する工法の導入を検討します。初期費用は高くなる可能性がありますが、長期的に見れば修繕コストの削減につながる可能性があります。
複数パターンの修繕積立金シミュレーション
値上げ幅の検討
18年サイクルに変更した場合に必要な修繕費用を賄えるよう、修繕積立金の最適な値上げ幅を複数パターンでシミュレーションします。
段階的な値上げの検討
一度に大幅な値上げを行うのではなく、段階的な値上げや、不足額を補填するための臨時徴収なども選択肢として検討します。
将来的なインフレ率の考慮
建材費や人件費の変動(インフレ)も考慮に入れ、余裕を持った積立金計画建てることが重要です。
3.居住者様への説明と合意形成
 修繕積立金の値上げを伴う変更は、居住者様の理解と協力が不可欠です。
修繕積立金の値上げを伴う変更は、居住者様の理解と協力が不可欠です。説明会の開催
複数回にわたり、理事会主導で説明会を開催します。
変更理由の明確化
なぜ12年サイクルから18年サイクルに変更するのか、そのメリット(例:工事費用の削減、居住者の負担軽減、生活への影響の最小化など)とデメリット(例:劣化リスクの管理、積立金の値上げなど)を具体的に説明します。
建物診断結果の共有
専門家による建物診断の結果を分かりやすく提示し、現状の建物の状況を共有します。
新たな長期修繕計画の詳細説明
18年サイクルでの具体的な修繕項目・時期・費用などを詳細に説明します。
修繕積立金値上げの必要性
シミュレーション結果を提示し、修繕積立金値上げの根拠と必要性を丁寧に説明します。複数の値上げパターンや段階的な値上げ案を提示し、居住者様の意見を募ることも有効です。
質疑応答の時間の確保
居住者様の疑問や不安を解消するため、十分な質疑応答の時間を設けます。
資料の配布
説明会で用いる資料や、長期修繕計画、修繕積立金シミュレーションの結果などを事前に配付し、居住者様が内容をじっくり検討できる機会を提供します。
アンケートの実施
居住者様の意見や要望を把握するため、アンケートを実施することも有効です。
専門家(マンション管理士等)の活用
- 居住者への説明や合意最終的には、管理規約に基づき、総会での決議が必要です。十分な説明と質疑応答を経て、居住者様の過半数以上の賛成を得られるよう努めます。
- 合意形成のプロセスが最終的には、管理規約に基づき総会での決議が必要です。十分な説明と質疑応答を経て、居住者様の過半数の賛成を得られるようにします。
4.実行と継続的な管理
 変更が決定された後も、継続的な管理と見直しが必要です。
変更が決定された後も、継続的な管理と見直しが必要です。定期的な建物点検と計画の見直し
18年サイクルで計画を立てたとしても、定期的な建物点検は継続し、予想外の劣化や損傷があった場合は、計画を柔軟に見直す必要があります。
修繕積立金の運用
積立金を効率的に運用することで、将来の修繕費を補填することも検討できます。ただし、元本割れのリスクも考慮し、慎重に行う必要があります。
居住者様への情報提供
定期的に修繕積立金の収支状況や、長期修繕計画の進捗状況を居住者に報告し、透明性を確保します。
最後に
マンションの大規模修繕サイクルを12年から18年に変更するということは、「将来を見据えた計画性」と「居住者様との丁寧なコミュニケーション」が最も重要となります。専門家を交えながら、現状を正確に把握し、現実的な長期修繕計画と修繕積立金計画を策定し、そして何よりも、居住者様一人ひとりが納得できるような丁寧な説明と合意形成のプロセスを踏むことが、成功への鍵となります。