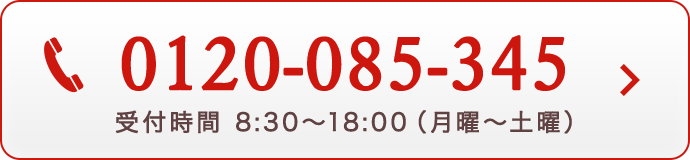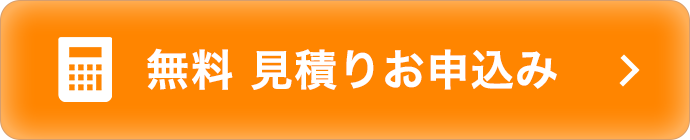ネットで賃貸マンションオーナー様より外壁タイルの調査・診断の依頼を頂き、3週間後に提案書を提出の後着工が決まりました。このマンションは築27年の建物ですが、今まで大規模修繕工事を行なっていません。その為、赤外線装置法での外壁タイルの調査を実施されましたが、対象となる部位は廊下・バルコニーの手摺壁(外側)のみでした。均一な日射のない廊下・バルコニーの内壁や妻側庇の一部は対象外となっています。結果的に全面的な改修工事を決断された建物です。
平成20年の建築基準法12条に基づく特殊建物「階数が3階以上に共同住宅を有し、かつ延床面積が1000㎡を超える」建物の定期調査のため、その内容を特定行政庁に報告を義務付けられています。改正による見直しのポイントは、「手の届く範囲を打診、その他を目視で調査し、以上があれば全面打診等によって調査し、加えて竣工、外壁改修等から10年を経てから最初の調査の際に全面打診等により調査」とあります。つまり、築10年を超える特殊建物(マンションや共同住宅の一定の規模の建物)については、大規模修繕工事等の外壁改修工事を実施していないケースでは、10年目以降の実施予定日まで全て全面打診等による調査報告の義務が伴うという事になります。
しかし、全面打診調査を行なう為には足場やゴンドラ・ブランコ・高所作業車等の架設が必要になり、この費用負担は大きいため、査診断のみで実施する事は一般的には行われていません。このような事情を考慮して、国土交通省住宅局建築指導課 監修「特殊建物等定期調査業務基準(2008年改定版)」では、「足場等を設置してテストハンマーで全面打診する方法」以外にも、「赤外線装置法」が「全面的なテストハンマーによる打診等」に相当するとしています。しかし、この方法は、適用限界が有るため、この調査だけでは正しい判断に結びつかない事もあります。
開口部の周囲のうち上部(まぐさ部分)や庇軒天鼻先廻りは、鉄筋のかぶり厚さの不足が生じ易い事や、重力作用でコンクリート下地と貼り付けモルタル間や、貼り付けモルタルとタイルの間で剥離が生じやすい部位です。
しかし、この部分は太陽の直射がない、室内と室外の温度差がある事などの理由から、一般的に赤外線装置法の適用限界外となる事が多い。タイル外壁の出隅部も浮きやひび割れが生じやすい部位ですが、赤外線装置法では浮きを見落とす恐れもあります。これらの部分は双眼鏡による目視検査や、打診調査を併用する必要があります。
赤外線装置法の適用ができないケースは以下の通りです。
① 雨天又は曇天で日中の気温差が少ない日。
② 軒裏、出隅、日陰になる部分、窓枠付近、凹凸の激しい部分。
③ 浮き代を伴わない(空気層が内)場合。
④ パールタイル等反射率の高い材質の場合。
⑤ タイル下地が熱容量の小さい(薄いボード)場合。
⑥ 建物と赤外線カメラとの間に障害物がある場合。
パールハンマーでの打診調査(テープの範囲 浮き ☓ ひび割れ)
手摺壁のひび割れ
最新記事 by 坂野宏三 (全て見る)
- マンション大規模修繕工事における談合事件について - 2025年10月10日
- 屋上防水工事 改質アスファルトトーチ工法 2024.11.25 - 2024年11月27日
- 屋上塩ビシート防水改修工事 2024.05.30 - 2024年5月30日
- エントランス前スロープ設置・自動扉改修 2024.05.13 - 2024年5月13日
- 機械式駐車場パレット補修塗装のポイント - 2023年12月22日